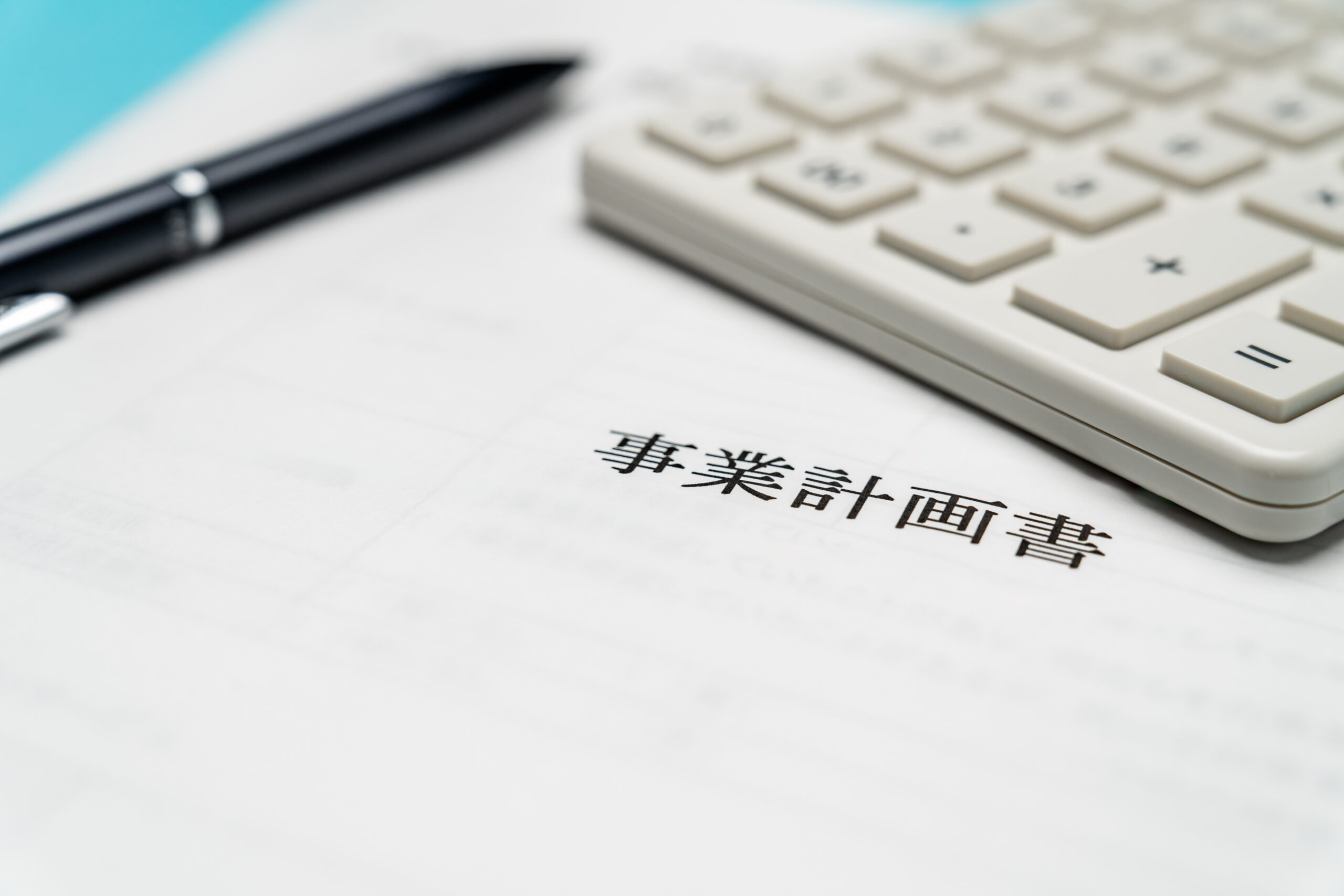開業準備を進める獣医師が不安に思う「失敗」のリスク
「いつかは自分の動物病院を開業したい」と考えていても、頭をよぎるのは“失敗したらどうしよう”という不安ではないでしょうか。
診療圏調査、資金計画、CTや超音波診断装置などの医療機器導入、スタッフ採用、広告戦略など、開業準備には多くの工程があります。
この中で一つでも判断ミスや遅れがあると、開業後に経営がうまく回らないケースも少なくありません。特に動物病院は専門性が高く、一般的な店舗ビジネスとは違ったリスク構造を持っています。
そこで今回は、動物病院の開業支援の現場でよく見られる失敗例とその原因、回避策を具体的にご紹介します。
よくある質問・困りごと:実は「失敗例」を知らないまま開業してしまう
開業を検討する獣医師や経営者から、次のような相談を受けることがよくあります。
- 「開業の失敗例って、どんなパターンが多いんですか?」
- 「何に気をつければ、リスクを減らせるんでしょうか?」
- 「立地は良いはずなのに、来院数が伸びないって本当にあるんですか?」
- 「CTや検査機器を揃えたのに、思ったより収益が上がらないという話を聞いた」
- 「スタッフの離職やチーム崩壊が開業直後に起こるって本当?」
- 「資金計画や融資で失敗する人が多いと聞いて不安です」
これらの質問は、開業準備の“成功のやり方”ばかりが注目され、失敗の実例が知られていないことが背景にあります。事前にありがちな失敗パターンを理解しておけば、対策を立てることができます。
動物病院開業でよくある失敗8選
1. 診療圏調査・立地分析の不足
競合病院の数や飼育頭数、交通アクセスなどを十分に調査せずに立地を決めてしまい、開院後に来院数が伸びないケース。
「なんとなく良さそう」で決めるのは危険です。
2. 資金計画の甘さ・融資準備の遅れ
土地・建物・機器・内装・広告・運転資金など、総費用を正確に把握せずに開業準備を進めると、途中で資金が足りなくなるリスクがあります。
融資手続きも時間がかかるため、早めの計画が必要です。
3. 設計段階で診療動線を考慮していない
診療室、手術室、ICU、検査室、トリミングスペースなど、動物病院特有の診療動線を考えない設計をすると、開業後に使い勝手が悪くなり、スタッフの動きが非効率に。
特にCTやレントゲンの配置は慎重な設計が必要です。
4. 医療機器の納期遅れ・導入計画のミス
超音波診断装置、血液検査機、生化学検査機、麻酔器、ICUケージなど、納期に時間がかかる機器もあります。
発注が遅れると、開業日に機器が間に合わず診療ができないという事態にもなります。
5. スタッフ採用の遅れ・教育不足
動物看護師や受付スタッフの採用が間に合わず、開院直後から人手不足に陥るケースは非常に多いです。
採用がギリギリになると、十分な教育ができず、離職リスクも高まります。
6. 広告・集患戦略の後回し
開業間近になってWebサイトやSNS、地域広告の準備を始めても間に合いません。
内覧会やGoogleビジネスプロフィール対策など、集患戦略は開業の半年前から始めるのが理想です。
7. 開業スケジュールの遅れが連鎖的に影響
一つの工程(立地選定・融資・設計・機器発注など)の遅れが、他の工程に連鎖し、開業全体が後ろ倒しになるパターンです。
余裕を持ったスケジュールと進行管理が不可欠です。
8. 開業後の経営改善・マーケティングが不十分
「開業したら患者が自然に集まる」と考えてしまい、開業後のマーケティングや経営分析を怠るケース。
開院後1年は来院数の変動が大きいため、定期的な見直しと対策が必要です。
失敗例を事前に知っておくことで得られるメリット
これらの失敗例を事前に理解して準備することで、以下のようなメリットが得られます。
- 来院数や収益の伸び悩みといった重大な失敗を未然に防げる
- 融資や機器導入の遅延による開業延期リスクを回避できる
- 診療動線の最適化やスタッフ育成を通じて、開業初日から効率的な診療体制を整えられる
- 広告・マーケティングを計画的に進められ、地域に定着しやすくなる
- スケジュール管理がしやすくなり、精神的にも余裕を持って準備できる
つまり、失敗例を知ることは“リスク回避の第一歩”です。
【まとめ】本郷いわしやなら、現実的な開業支援が可能
株式会社本郷いわしやは、動物病院の開業支援・導入支援で数多くの成功・失敗事例を蓄積しています。
診療圏調査・資金計画・設計・機器導入・集患戦略・スタッフ採用までを一貫してサポートし、失敗リスクを最小限に抑えた現実的な開業プランをご提案できます。